〇この記事を読むのに必要な時間は約3分7秒です。
依頼者:札幌市厚別区在住 20代女性
相続人2名(配偶者、長女)の事案で、依頼者は被相続人の一人娘である方でした。
母が病死し、相続人は父と依頼者の2名でした。
母は、遺言書を残さず亡くなり、父は、母の財産はすべて自分のものであると譲らず、依頼者の年齢が若いこともあって話し合いに応じない状況でした。
依頼者は、父の関係がもともと良好とはいえない状況だったため、自身にて父と遺産分割協議を行うことは難しいと考えていました。
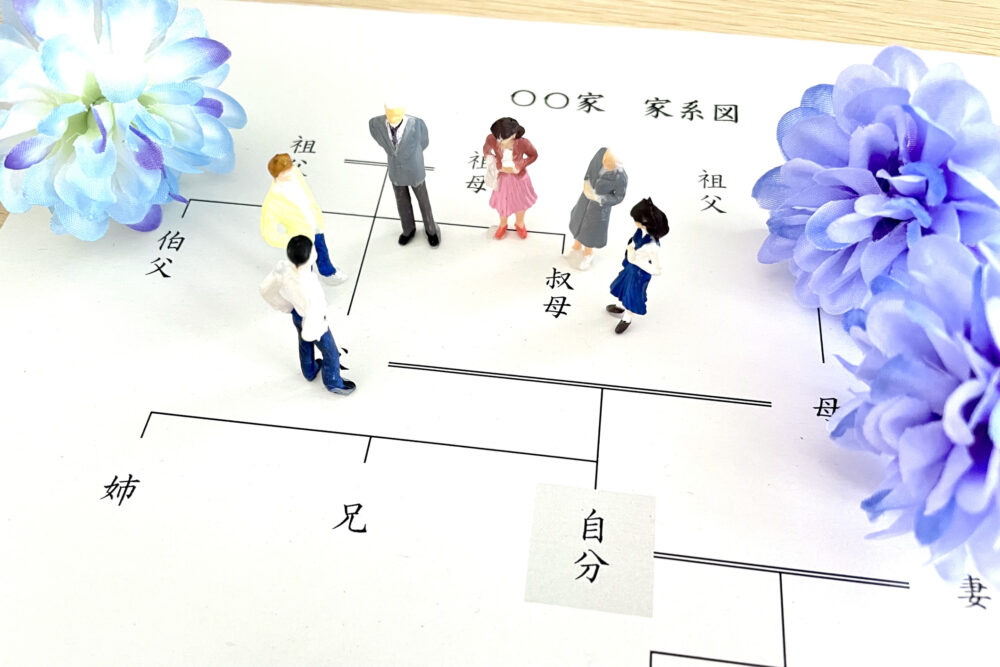
この事案では以下の点が解決を困難にしていました。
・遺産には不動産の共有持分が含まれ、査定評価が必要
・遺産資料はすべて相手方である父が保管し開示に応じない
・父は母の遺産は夫婦のものと主張し依頼者に遺産分割する意向がない
相手方である父が遺産資料の開示に応じないため、金融機関や生命保険会社へ遺産についての照会を行い、不動産の査定を実施しました。
相手方である父は、分割に応じない強い意向を持っていましたが、弁護士から遺産分割協議が成立しない場合の双方のデメリットや、遺産に父が居住する不動産持分も含まれているため自宅を失う可能性等を丁寧に説明し、調停に至らずして遺産分割協議を成立することができました。
不動産や預貯金等は相手方である父が単独取得し、依頼者は代償金として金銭のみを取得することになりました。
依頼者はもともと早期に金銭を取得して解決すること、相手方である父が自宅を失うことは希望しない、との意向だったので、双方が納得しての解決となりました。
父か母が亡くなった場合に、一方の親がいったんすべての財産を相続する方向で遺産分割協議が成立することが多いのですが、親子間の関係性によっては、紛争になることも数多くあります。
特に親側に遺産は夫婦の財産という意識が一方に強い場合は、感情的になりやすく円満な協議がしにくいと言えます。

相続について、民法上のルールとは異なる独自の「常識」をもって強く主張する方が相続人にいる場合、当事者間での協議は非常に困難です。
しかし、協議が成立しない場合は、法的手続に進行することを相手方へもアドバイスしながら、調停等を行わず解決できるケースも多いため、是非「弁護士法人リブラ共同法律事務所」へご相談下さい。

弁護士法人リブラ共同法律事務所
弁護士 髙橋 亜林
相続、離婚など家事事件




